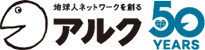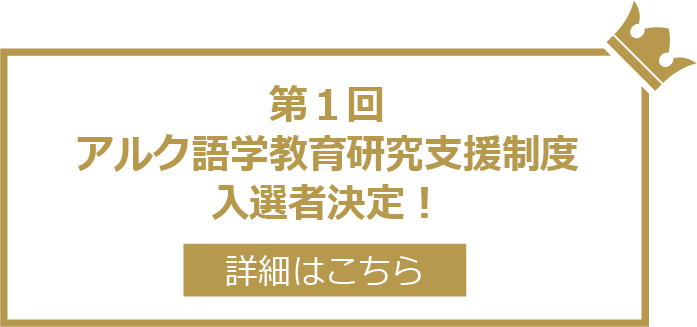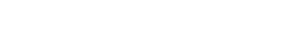
なぜ今、アルクは研究支援制度を創設するのか
アルクは2019年4月に創立50周年を迎えました。一貫して掲げてきた当社のミッションは「地球人ネットワークを創る」。言語教育を通して、国や文化の異なる人々の間のコミュニケーション促進に貢献してきました。
当社は、言語知識の獲得とその運用能力育成を言語教育における車の両輪と捉え、さまざまな教材、研修、テスト、学習支援サービスを開発・提供して参りました。
海外の人と一緒に仕事をする日本人と訪日外国人が飛躍的に増えた今、言語教育において継続的学びを通して、知識の定着や運用能力を向上させることが一層重要になってきました。この動きをさらに加速すべく、ここに「アルク語学教育研究支援制度」を創設いたします。
本制度のテーマは【継続学習を促す学習デザインの探求】です。
①ICTを利用した教材や教授法、②次の学習行動を促すような評価とフィードバックの方法、③教室での効果的言語活動モデルなどの分野において、継続的学習を促す研究を進める方々を本制度は支援します。本制度を活用した研究の成果が、新たな教材、教授法、評価法などの創出につながることを期待しています。
自分の考えを自分の言葉で表現し、多様な人々と信頼関係、協力関係を築いていくことができる言語能力の開発にアルクは挑戦し続けます。
アルク教育総合研究所
平野 琢也
研究支援の内容

1. 支援金:1件30万円以内。年3〜5件。研究内容に応じて支援額を決定します。
2. 現物支給:研究者から要望がある場合、アルクの著作物である英語スピーキングテストTSST、TOEIC®L&R模試、アルク学習語彙12000語リスト・SVLなど、アルクの各種教材やサービスを提供。支給の内容と数量は支援額と併せて検討し決定します。
3. 研究途中における助言:研究者からの中間報告を受け、必要に応じて専門家が助言します。
4. 支援期間:支援決定通知の月から原則1年間。研究期間の長短と支援内容は連動しないものとします。
研究支援分野
本制度の基本テーマ
【継続学習を促す学習デザインの探求】
■研究支援分野
A)ICT利用教育、反転学習のモデル創出などの分野:継続学習を促す教材・学習ツールの開発または利用方法の工夫とその効果検証
B)テスト・動機付け分野:次の学習行動を促すための評価法・フィードバック方法とその効果検証
C)Active Learning (AL) / Project Based Learning (PBL) の分野: 言語教育の場への「言葉を使う」活動の効果的導入方法とその効果検証
各分野における支援件数は応募内容に応じて検討します。
研究支援の対象者
個人の研究者、または研究者のグループ。個人またはグループが取り組む研究が途中のもの、他の助成を受けている研究であっても選考対象とします。他の研究支援を受けている場合は、本支援が必要である理由を提出する研究計画書の中の「7.これまでの準備状況」で明示してください。
選考委員

Photo by Shiho Hashimoto
委員長
根岸 雅史
東京外国語大学大学院教授
言語学習では、様々な学習が連続的に行われています。しかしながら、それらがすべて効果的につながっているかというと、そうとは限りません。また、つながっていればよさそうではあっても、それが真に効果的なのか、あるいはどうつながっていればいいのかといったことについては、まだまだわからないことがあります。
この度、アルクが創業50周年を迎えるに当たり、語学教育研究支援制度を始めました。現場の教員の方や学生などで、研究がやりたくても、そのための充分な財源がないとか、研究のノウ・ハウに関するアドバイスがほしいという方は少なくないでしょう。そうした方々からの、たくさんの応募があることを期待しています。

委員
髙橋 一也
工学院大学附属中学校・高等学校 中学校教頭
昨今、英語教育を取り囲む状況が急激に変化しております。小学校では英語教育の早期化が推進され、大学入試では英語の4技能が問われるようになりました。また、2020年の東京オリンピックを控え、英語でのコミュニケーション能力の必要性が声高に叫ばれるようになっております。同時に教育現場では、ICT技術の進歩により旧来の英語指導方法からICT機器を活用した教育方法や、英語で「何か」を学ぶCLIL(内容言語統合型学習)やPBL(Project Based Learning)などの指導法への関心が高まっております。本教育研究支援制度は新しい時代を切り開き、教育関係者すべてに資するような教育研究を応援したいと思っております。皆様方からの素晴らしい研究実践を伺うことを何よりも楽しみにしております。

委員
廣森 友人
明治大学教授
日本の英語教育を長きにわたって様々なレベルでサポートしてきたアルクが今回、新たに「研究支援制度」を創設してくださったことに、まずは率直にお礼を申し上げたい。アルクがこれまで蓄積してきた強力なコンテンツと日頃から先生方が温め、育ててきた貴重なアイディアが出合うことで、英語教育に新たな化学変化が起こることを確信しています。本制度のキーワードのひとつは「継続学習」です。我々はとかく学習の開始時に目を向けがちですが、英語を身につけるには長く地道な取り組みが欠かせません。継続的かつ自律的に学習に取り組む生徒にはどんな特徴があるのか、そのような学習を促すプロセスやメカニズムとはいかなるものか。この制度を通じて、そういった課題の解明に正面から向き合う研究が数多く生まれることを期待しています。

委員
水本 篤
関西大学教授
今回、アルク創立50周年企画「アルク語学教育研究支援制度」の申請者に期待することは、これまでの外国語教育学、応用言語学の分野としての研究の積み上げをしっかり理解し、その上で、これまでの枠組みを越えていくような試みをしてほしいということです。新しい研究の創出は、既存の研究の理解なしには不可能です。ぜひそのつながりを重視し、自分の研究課題や目的に応じて、必要な手法を選択していってもらいたいと思います。本制度の基本テーマは、「継続学習を促す学習デザインの探求」ですが、研究分野は広く設定してあります。できるだけ多くの方が新しい刺激的な研究を、この制度によって形にしていけることを願っています。

委員
森田 光宏
広島大学准教授
「継続は力なり」と言いますが、自分が何かを継続する以上に、生徒や学生に継続的に学習をさせるのは大変な力が必要です。特に、言語学習は、不断の努力を必要とする地道な道のりです。それでも、努力が報われる瞬間が度々あり、その実感が歩みを進める原動力になります。本助成から、地道な道のりを学習者と共に歩むような、地に足の着いた研究が生まれることを期待しています。そして、学習者に言語学習の喜びを実感させる取り組みが生まれることにも期待を寄せています。本助成の成果の一つ一つが、指導者と学習者にとって、長く険しい道のりを楽しく歩いて行ける道標となることを願っています。
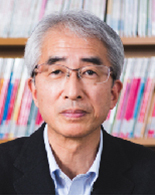
委員
平野琢也
アルク教育総合研究所
選考基準
1. 応募書類が必要条件を満たしていること
2. 研究内容の教育的有用性、実現可能性
上記を総合的に勘案して決定します。
研究成果公開
1. 研究結果は、研究支援開始月の1年後にアルクに報告することを原則とします。
2. 研究成果の公開に関し、研究成果の学会発表を目指す場合は、それを優先的公表の場として考慮します。
3. 可能な場合には、「アルク英語教育実態レポート」、アルクのWebサイト、アルク主催各種イベント等で発表していただきます。
4. 研究結果に応じて商品化(書籍化)を検討します。
スケジュール
1. 申込み受付開始日:2019年6月1日(土)
2. 申込み受付終了日:2019年8月30日(金)
3. 結果通知時期:2019年10月中旬
4. 研究結果報告期限:2020年9月末日
研究支援制度細則
■支援金支給について
支援金は、応募者が支援決定通知を受領した日以降に使用可能となります。
詳細は別途、支援対象者に通知します。
なお、以下に該当する場合には、支援金または支給した現物の一部または全部の返還を求めることがあります。
(1) 虚偽の申し出または報告を行ったとき
(2) 支援対象となる研究活動等が中止となったとき
(3) 支援期間終了後、支援金の未使用金があるとき
(4) その他、弊社が研究支援の目的に照らして妥当でないと判断したとき
■契約について
支援対象者とアルクは契約を締結し、研究支援の詳細、守秘義務、個人情報保護などに関わる事柄を規定します。
応募方法
第一回の募集は終了しました。
第二回の募集は、2020年6月頃の予定です。
お問い合わせ